防音室の骨組みを作る
写真は、防音室骨組みになる材料です。
主に防音室の柱として利用したツーバイフォー材というもので、DIYショップでよく見かけます。
最近はウッドデッキや日曜大工の材料としてもよく使用されているもので、今回は38×89ミリのものです。
材料切断には電動の丸のこ(左写真)を使用しました。
慣れるまでは大変危険な道具ですが、これがないとスムーズな作業が期待できませんが、万能のこぎりでも十分です。
防音室に制作ぜったい必要な道具としては、こののこぎりと、コンベックス(メジャー)、(※1)ドライバードリル、ハンマー、巻金ぐらいでしょうか。
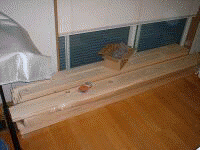
巻金を購入する際は尺や寸目盛りのものがありますので気をつけてください。
材料の木材同士の結合には、釘や、木ねじ(コーススレッド等)を使います。図面から寸法を割り出し、あらかじめ材料をカットしておきます。
(※1)釘で製作されるかたはいりません。
あとで解体する必要がある方はくぎを使わないでネジどめすることをおすすめします。

防音室の骨組みを作ります。
ツーバイフォー材は2×4工法(壁パネル工法ともいう)といい、枠組みしたものにベニア等の壁をうちつけていき、できたパネル同士を箱状にして部屋をつくるもので、非常に簡単にできます。
基本的にのこぎりとハンマーがあれば作れます。
この方法で自宅を自分で立てられた方もいらっしゃいます。
管理人の愛読書です。防音の本ではないけれど、スタジオ製作に役立った実用的な本です。
マイホームまで出来なくても、ガレージや大きな物置、倉庫なんかに応用できます。
材料の仕入れ方や道具などのヒントがぎっしり詰まっていて、読むだけでワクワクします。
素人でもかなりの大物が作れるので、今回はこれを応用して作ってみました。
写真は奥の壁となる枠と手前の枠を仮に組んでみたところです。
この場合電動ドライバードリルがあれば楽に作れます。
私が使用したリョービドライバードリル FDD-1000 (左の写真)はプロユースとしてはもの足りませんが、家庭用ではかなりオススメで、これ1台で穴あけできるしドライバにもなります。
2台買って、穴あけ専用とドライバ専用にすればかなり仕事がはかどります。
またすこし高価ですが、作業性を重視するならお小遣いに余裕のある方は充電マルチインパクトドライバーが絶対にオススメです。
コードを引っ張ったりしなくても済みますし、何しろ使いやすい!私も仕事では当然充電式を使ってます。(笑)

柱の底の枠は1×4材(厚さ19㎜幅89㎜)で、枠組みし、柱を底からネジ止めしてあります。
また、防音室用に底には防振、音洩れ対策用の防音マットを敷くほうがいいと思います。

解像度が悪いので分かりにくいのですが、2×4材の壁になる柱の内側部分へ、パネルを差し込む溝を彫ってあります。
この作業にはトリマーという道具があれば見た目も美しく簡単に溝が掘れますが、価格が高価なのであまりお勧めしません。
あとあといろいろな作業に使いたいという方は買っておいてもいいと思います。
私はたまたま持っていたので使いましたが、溝を掘って差し込まなくても、外側から釘止めでいいと思います。内側から壁を作ってしまうと、防音のための防音材(グラスウールやマット類)を重ねることができなくなってしまいます。
つまり、この分厚い柱の中に防音材を詰め込んで、パネルでサンドイッチしてしまおうということです。
防音材については、いろいろなやり方があるようで、グラスウール+防音シートだとか、吸音タイプの防音室(楽器や声が反響しない)の場合はスポンジのような防音材をむき出しにして壁一面に貼ったり、サンドイッチしたべニアに無数の穴(多穴板)を張り付けるだとか、いろいろあるようです。
私はたった3日で仕上げなければならなかったので、もらい物の建材を利用しましたが、時間がある方は、いろいろ考えながら試しながら作成しても面白いと思います。
要するに防音のための隙間をできるだけ少なくした作り方をすればいいだけです。
2018年7月21日 更新
